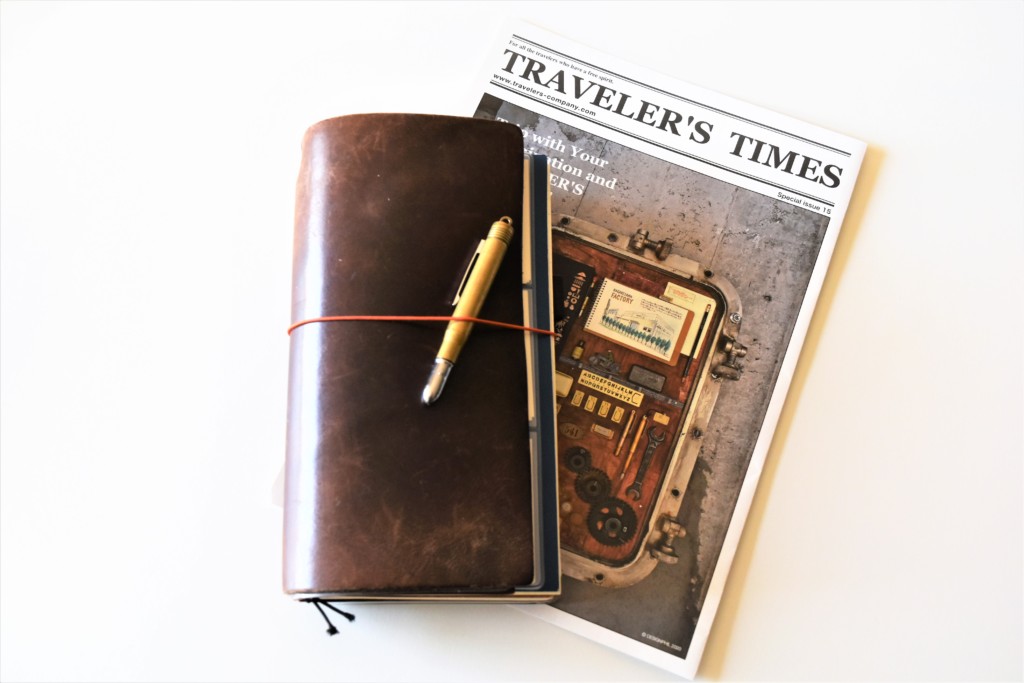お蕎麦でおなじみの「蕎麦猪口」。雰囲気が出ますし、実際に蕎麦猪口で食べるとお蕎麦が美味しいですね。
でも、夏のお蕎麦や冷や麦シーズンにしか使わないのは、ちょっともったいないかもしれません。
きょうは、オールシーズン使える「蕎麦猪口の使い方」を、このページでご紹介いたします。
蕎麦猪口の模様は、それはもうたくさんの種類があるので、「魅力的な珍しい食器」と言えます。
コロンとした可愛い蕎麦猪口。口が大きいので使いやすい蕎麦猪口。いろいろな使い方で「おしゃれな蕎麦猪口生活」を始めてみませんか。
「蕎麦猪口」の使い方は多様です

蕎麦猪口は、お蕎麦を食べるだけに使う器としてだけでなく、日本酒や焼酎、ワインなどの飲み物を入れる器として使っても楽しめます。
蕎麦猪口を使ったアイデアをご紹介いたします。
飾る

夏が終わったら、食器棚の奥に仕舞ってしまうのは、ちょっともったいないですね。
わが家は、オールシーズン蕎麦猪口を「水屋箪笥(みずやだんす)」に置いて飾っています。
お客様が見えたとき、「好きなの使ってね」と言って、選んでもらっています。
湯のみとして
 お茶を入れて湯のみとしても使えます。
お茶を入れて湯のみとしても使えます。
口が大きいので飲みやすいですよ。素敵な湯のみが欲しいなと思われている方は、蕎麦猪口をお探しになると、きっと素敵なものと出合えるかもしれません。
食器として

フルーツ、サラダをちょこっと盛り付けするのに便利な蕎麦猪口。
大きさに多少バラつきがあっても、蕎麦猪口で揃えると、おしゃれに見えますね。
焼酎、日本酒の器に

昔、三軒茶屋に住んでいたとき、焼鳥屋さんさんが蕎麦猪口でお酒を出していました。それ以来、日本酒や焼酎をいただく時は、わたしも蕎麦猪口派です。
デザートの器に

プリンやムース、ゼリーの器として使うと、涼し気です。
花器としても

切り花や、エアプランツを挿すだけで、しっとりとお部屋を彩る花器になります。
コーヒーやココアにも

蕎麦猪口の魅力は、どんな器ともマッチするところです。
美術品であり、民芸品でもある「蕎麦猪口」
蕎麦猪口は今から300年前の江戸時代から作られはじめました。
原点(ルーツ)は、古伊万里と言われています。ツルンとした磁器に藍色の絵柄が描かれた古伊万里が、日本全国へ広まってゆきました。
当時の蕎麦猪口は、もちろん一つ一つが手作りです。昔は安価な蕎麦猪口も、現代では骨董品として立派な美術品になりました。
しかし、私個人の見解は、江戸時代から親しまれて使われていた蕎麦猪口を、使わないで大事に仕舞って置くことはせず、「民芸品(雑器)」として扱いたいと思っています。
わたしは「柳宗悦(やなぎそうえつ)」さんを師匠とあがめているのですが、著書「藍絵の猪口」で、
「いかに日本人が自然を友にしたかが分かる」
と記しています。先人たちが残した優れた民芸を、現代の私たちも大事に使って継承してゆきたいですね。
模様を楽しむ「蕎麦猪口」

昨今、無印良品のシンプルな蕎麦猪口や、スタイリッシュなデザインの蕎麦猪口が市場に多く出ていますね。時代の変遷とともに、蕎麦猪口も変わってきています。
蕎麦猪口ほどバラエティーに富んでいる「楽しい器」は、他にはないのではないでしょうか。
冒頭でもお伝えいたしましたが、蕎麦猪口の模様は多岐にわたり様々です。植物、動物、風景、幾何学模様。
もし蕎麦猪口をお求めになりたい方は、先人が使っていた蕎麦猪口をオススメいたします。
大量生産でない「職人の手で描かれた藍色の蕎麦猪口」は、必ずやあなたを魅了してくれるはずです。
カジトラコレクションのご紹介
わが家で使っている愛用品を、ご紹介いたします。
下北沢の骨董屋にて

2010年に下北沢の骨董屋さんで購入した蕎麦猪口です。お店の名前も覚えていないのですが、「目が合った」ので買いました。
一個あたり4千円ほどだったと思います。あまり値段も覚えていないのですが、OLが求められる金額でした。
模様については、現在、鋭意勉強中ですので、別の記事で蕎麦猪口の模様について、ご紹介できればと考えております。

初めて使った日の写真です。
実家の土蔵から発見

実家の土蔵を取り壊すことになった時に出てきた蕎麦猪口です。
いつから、だれが使っていたかも分からないものですが、私の相曽祖父母(ひいおじいちゃん・おばあちゃん)が使っていたものかもしれません。
父から譲り受けて、大切に使っています。
不思議な「見込み」

「見込み」をご存知ですか?
器の内側の部分を「見込み」といいます。古い蕎麦猪口の見込みは、可愛い模様が描かれています。
絵柄は、草花、昆虫、動物、紋章など多岐にわたります。
わが家の絵柄は一体何なのか、いまだにナゾなのです。(夫は、白菜と言っています)

左の絵柄は、たしかに白菜に見えなくもありませんね。右のは笹船か、亀でしょうか?
どなたかご存知でしたら、教えてください。
オススメの蕎麦猪口
個人的には、前の章でご紹介しました「見込みに、絵が描かれている蕎麦猪口」をオススメします。
当時の職人さんが手描きした絵柄を、数百年後の私たちが使うことは、とても素敵ではありませんか。
いかがでしたでしょうか。いろいろな蕎麦猪口の使い方をご紹介いたしました。
時には湯飲み、時には花器など、使い方は無限に広がりますね。
可愛い蕎麦猪口で、オールシーズンおしゃれに暮らしませんか?
これからもこのページで蕎麦猪口の使い方をご紹介してまいりますので、また遊びにいらしてください。