
梅雨が明け、小暑、大暑が続く7月(旧暦6月)は、畑の野菜たちがもっともよく育つ月になります。
今回は、昔農家さんから学ぶ7月の農作業について、ご案内いたします。
昔の農家さんは、私たちよりも はるかに季節の移り変わりに敏感で、植物や動物の動向などを観察しながら、農作業を行っていました。
先人の知恵は、現代を生きる私たちの野菜づくりのヒントになるものが数多くありますので、参考になさってください。
※ 掲載の画像はすべてイメージです
昔農家さんから学ぶ7月の農作業について
梅雨明けの7月は、日差しが強くなり、気温が高くなりますので、体力が消耗します。
水分と塩分を摂取し、適度に休息しながら、畑仕事をなさってください。
朝顔が咲いている間に農作業

日差しと気温が高くなる7月、昔農家さんは 涼しい朝のうちに作業をし、日中は昼寝をして体を休め、そして夕方に野良仕事を行っていました。
私たちも、炎天下での作業を避けて、朝顔の花が咲いている涼しい朝に農作業を行いましょう。
アブラゼミ・ヒグラシの初鳴き

アブラゼミや、ヒグラシが鳴き始めましたら、夏ニンジン、キャベツ、ブロッコリーなどの種をまきます。
7月の農作業(例)
| 二十四節気 | 時期 | おもな畑仕事 |
| 小暑 | 7月7日頃 | ・夏野菜の収穫 |
| ・夏まきキャベツ、ニンジン、カリフラワーの種蒔き | ||
| ・ネギの定植 | ||
| 大暑 | 7月22日頃 | ・サトイモの土寄せ、潅水 ・イチゴのランナーから苗をとる。仮植え。 |
※地域によって前後します。(参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」)
7月の農事歴
私たちは現在 新暦(太陽暦)にて暮らしておりますが、江戸時代以前の農家さんたちは、旧暦にて農作業を行っていました。
旧暦の農事は、現代においても参考になり、野菜づくりの良き指標となるかと思いますので、ご案内いたします。
7月の農事歴[旧暦6月(水無月)]
| 1日 | [雑]半夏生 |
| 2日 | |
| 3日 | |
| 4日 | |
| 5日 | |
| 6日 | |
| 7日 | ◎小暑(旧暦6月1日頃) |
| 8日 | |
| 9日 | ◇温風至る |
| 10日 | |
| 11日 | |
| 12日 | |
| 13日 | ◇蓮始めて花咲く |
| 14日 | |
| 15日 | |
| 16日 | |
| 17日 | ◇鷹すなわち学習す |
| 18日 | |
| 19日 | [雑]土用入 |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | ◎大暑 |
| 23日 | |
| 24日 | |
| 25日 | ◇桐始めて花咲かす |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | |
| 29日 | ◇土潤うて溽暑す |
| 30日 |
◎ 二十四節気 ◇ 七十二候 [雑]雑節
参考文献 久保田豊和著「新版 暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二ヵ月」
[雑]半夏生(はんげしょう―新暦7月1日頃)

夏至から数えて11日目です。
この頃、梅雨が終わりに近づき、田植えを終わらせる時期でもあります。
なお「半夏(はんげ)」は、仏教用語で、各地の僧侶が一堂に会する90日間の修行「下安居(げあんご)」の中間日です。
◎小暑(しょうしょ―新暦7月7日頃)

日差しが強くなり、梅雨明けが近くなってきた時期で、この頃からセミが鳴き出します。
◇温風至る(あつかぜいたる―新暦7月9日頃)

夏の風が吹き始める時期です。
◇蓮始めて花咲く(はすはじめてはなさく―新暦7月13日頃)

朝の涼しい中で、蓮の花が咲く頃です。
◇鷹すなわち学習す(たかすなわちがくしゅうす―新暦7月17日頃)

鷹のヒナは、この時期に飛ぶことを覚えて、空に羽ばたきます。
photo by JoshuaJ.Cotten (Unsplash)
[雑]土用入(どよういり―新暦7月19日)

立秋前の18日間です。
夏の土用は、ウナギで有名ですね。
現在、「土用」は、おもに夏がクローズアップされていますが、各季節、春夏秋冬のおわりの18日~19日間をいいます。
◎大暑(たいしょ―新暦7月22日頃)
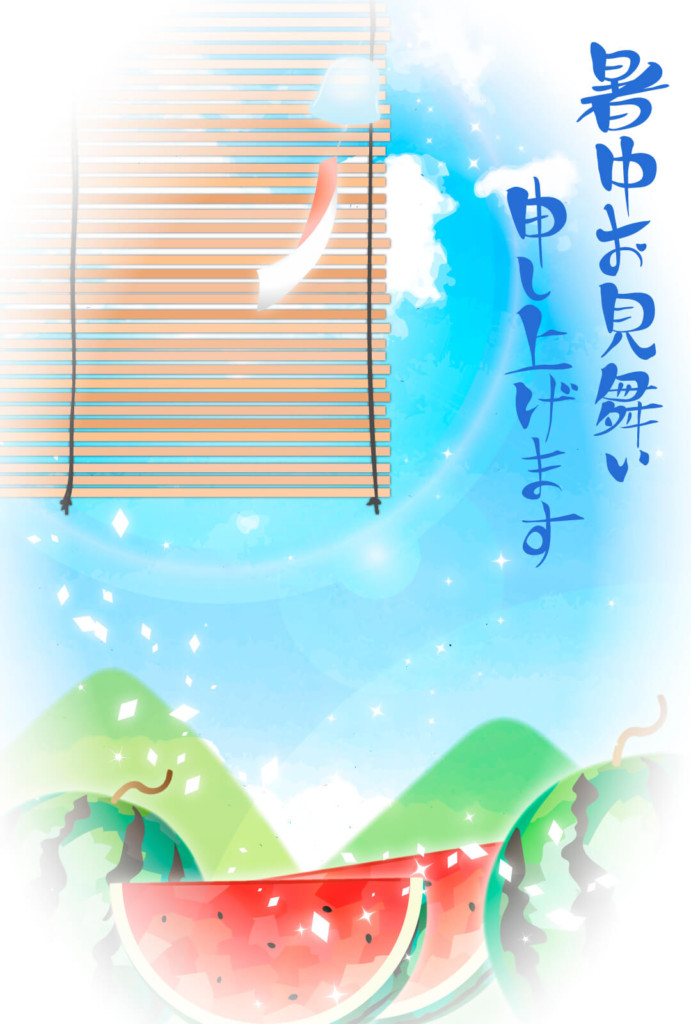
夏至から数えて、おおよそ一月後が「大暑」で、夏盛りの時期です。
蝉時雨(せみしぐれ)は、多くのセミがあちらこちらで盛んに鳴くことで、まるで雨が降ってきたかのようにセミの声が聞こえるという言葉です。
なお、小暑と大暑の間に出す便りが「暑中見舞い」で、大暑を過ぎたら「残暑見舞い」になります。
◇桐始めて花咲かす(きりはじめてはなさかす―新暦7月25日頃)

桐の花が咲き、実を結ぶ頃です。
phote by Studio Kleurrijk/133 images
◇土潤うて溽暑す(つちうるおうてじょくしょす―新暦7月29日頃)

溽暑(じょくしょ)とは、蒸し暑いという意味です。
この時期は、陽気が土を潤して、蒸し暑くなります。
まとめ

7月の農作業と農事歴について、ご案内いたしました。
昔の農家さんは自然と共存しながら農作業を行い、私たち現代人よりも、はるかに季節の移り変わりに敏感でした。
先人の知恵は、今を生きる私たちの野菜づくりのヒントになるものが数多くありますので、参考にしていただければ幸いです。
[参考文献]
・やさい畑 2020年冬号別冊付録 野菜づくりカレンダー


